声を上げれば変わる!障害福祉事業者のための政治活用術
.jpg)
グルホネットでは、障害福祉事業を経営する事業者様向けに事業のリスクマネージメントをテーマに役立つコラムをお届けしています!今回は、現役の市議会議員である山口大輔氏に、『自分たちの事業運営を良くするための政治との関わり方のポイント』について解説していただきました!
障がい福祉事業は運営方針が国の定めた省令・告示に大きく左右されます。改正が行われるたびに右往左往した経験が皆様おありではないでしょうか。
今年度もBCP、感染症、拘束、虐待など様々な行わねばならない規則が増えてきました。それに加え自治体単位で解釈が異なるローカルルールも存在します。障がい・介護といった福祉事業は、政治と密接な関係を持つ業種にかかわらず、事業者の方は政治と深く関わりを持つことがありません。声を上げていくことで変わる未来があります。
今回は現役ケアマネジャーでもある政治家として、自分たちの事業運営を良くするための政治との関わり方のポイントを解説したいと思います。
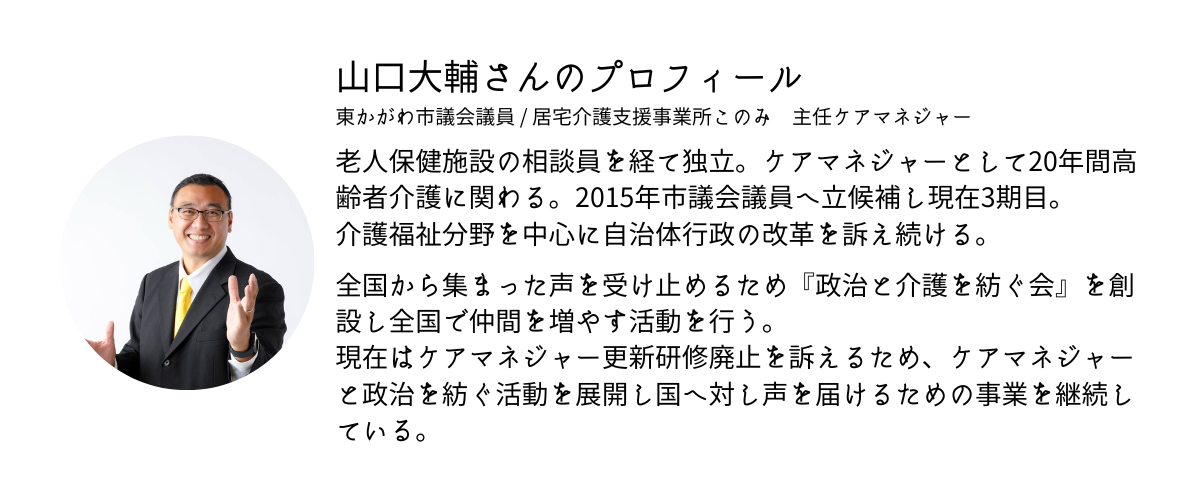
障がい福祉事業の現状と課題
安心安全の理念のもと導入される基準の数々
令和6年度より新たに業務継続計画未策定減算が加わったことで、昨年度末はどの事業所もこれらの制度導入に追われていたことと思います。また高齢者虐待防止措置未実施減算の導入もあり、今年度は確実な実施が求められるため本腰を入れだした事業所もあるのではないでしょうか。
過去にも様々な基準が増え、一定期間の移行期間の後に制度化され、福祉事業所に課せられた規制や基準はどんどん厳しくなっていきます。福祉とは安心安全であるものという理念のもと、今後もこういった規制が入ってくること思います。
業務継続計画(BCP)未策定減算とは
2024年度の介護報酬改定において導入された新しい減算制度です。この制度は、介護や障害福祉サービス事業所が自然災害や感染症の発生時にサービスを継続できる体制を整えるために、業務継続計画(BCP)を策定することを義務付けています。BCPを策定していない事業所に対しては、基本報酬が減算される仕組みです。
人材確保の難しさ
またこういった規制だけでなく、人員基準を満たさないと加算が取れない、または大幅な減算もあるため、どの施設も人材確保に必死のはず。特にサービス管理責任者は必須要件にも関わらず確保が困難な有資格者の1つではないでしょうか。
それにも関わらず受講要件を満たしても、サービス管理責任者等研修の定員に限りがあるため、研修自体が受けられず、なりたくてもなれない人も多く、人材が増えていかないというジレンマがあります。
行政とのコミュニケーションの難しさ
視点を変えて次は行政との関わり方です。申請を始め行政とは密着な関係があるはずですが、皆さんはこんなことにお悩みではないでしょうか。担当者が変わるたびに解釈が変わる
新年度いつものように相談に行ったとき、なぜか認めてもらえなかった。そんな経験はありませんか。担当職員が変わるとこれまで可能とされていた範囲が微妙に変わることがあります。また逆にこれまでだめと言われていたことがなぜか受理されることもあったはずです。
法律では詳細まで決めることが難しいため、ある程度は自治体の判断に委ねられるケースが多々あります。これが担当者が変わるたびに解釈が変わる理由です。
また担当職員も異動したてだと制度のことをよく理解できていないケースがあります。そのため詳細を聞いてもなかなか答えてくれないケースも有り、新年度はドキドキが止まりません。
ローカルルールが多い
担当者が変われば解釈が変わると説明しました。そのうえ多いのが自治体独自で作り上げているルールです。同じ自治体でしか働いていない方は気づきにくいことですが、書式や申請手順など自治体によって本当に違うんです。加えて自治体独自で求める書式などがあるので、新しく入った職員だけでなく、他自治体で勤務していた職員さんにとっても頭を悩ます原因になっているのではないでしょうか。
要望を伝えるための効果的なアプローチ
相談は行政ではなく政治家へ
何かを変えてほしいと思って行政に相談してもなかなか変わることはありません。基本的に決まったことを施行していく機関なので大きな問題がなければ指摘されてもすぐに検討に入ることはありません。ではどうしたらいいか。そういう時には政治家に相談することが解決の近道です。
権力があると間違わないでください。理由は政治家は行政の運営(執行)を監視し、疑問があれば質疑し、状況を確認していくのが仕事だからです。
例えば申請にあたってなぜか書かなければいけない様式があったとします。この場合なぜ必要なのか、それは条例などで必要と定められているものか、変えられない理由は何かといった詳細を確認していきます。
なによりも変更を希望しているという声があるということを訴えて質問していけるのが政治家の強みです。こういった行政の運用について確認していく専門家が政治家なので、気になることはどんどん相談していきましょう。
ただ1つだけ気をつける点があります。
要望では何も変わらない。政治家を動かす効果的なアプローチ
.jpg)
「これはおかしい、なんとか変えてほしい!」
この言葉だけでも政治家は動きます。でもちょっと待ってください。あなたが相談した政治家はその道の専門家でしょうか?
思いを受けて行政に質問しても、行政のほうが情報に詳しい場合回答が正しく聞こえることで、それ以上追求することができなくなる場合があります。また質問しても望む着地点には届かないケースも多々あります。政治家は行政の運用を確認する専門家ですが、決してあなたのお悩みごとの専門家ではないのです。まずここを抑えてください。そのうえで政治家に思いがより伝わるためのノウハウをお伝えします。
それは、感情に訴えるのではなく、①お悩み事の具体化、②ゴールの言語化、③根拠(エビデンス)を伝えることです。
①お悩み事の具体化
誰がどう困っているのか、それによってどういうデメリットが発生しているのか。
②ゴールの言語化
具体的に何をどうしてほしいのか。
③根拠(エビデンス)
変えるべき根拠(他自治体にはない、ある、法令で求められていない等)
これらを整理したうえで政治家に渡すと、質問の趣旨が作りやすく相談者と同じゴールを見ることが出来ます。相談しても何も変わらなかったというのは、このアプローチが十分できていなかったからだと思います。
難しく考える必要はありません。新しく何かを実践する時に皆さんは企画書をかくと思います。それと同じものを作って渡すだけです。
相手に自分の思いを理解してもらうための一手間をぜひかけてみてください。
改正事例から学ぶ成功のポイント
これらのアプローチをしても残念ながら自分の思いと100%一致するような改正はなかなか叶いません。どうしてもどこかで妥協点を見出すことになります。それでももっと想いが届いたら・・・そう思った方はぜひ自分が政治家になって直接声を届けるという活動をしてはいかがでしょうか。ここでは現役介護職議員だからできた、いくつかの介護保険に関する改正事例のポイントを紹介したいと思います。

福祉用具購入、住宅改修費用の受領委任払を実現
過去にも質問が上がっていましたが採用されることはありませんでした。そこで回答にあった「受領委任払を導入すると業者が嫌がるのではないか」という一文に注目し、制度が採用されている自治体にいる事業所にアンケートを取りました。結果は導入が望ましいという声がほとんどでした。このデータを見せて改めて質問したところ、相手の反対する理由がなくなったため翌年度より受領委任払制度が実施されることになりました。
ケアマネジャー更新研修費の補助金支給へ
更新研修が負担になり離職するケースも多いケアマネジャー。数の減少から自治体のケアマネジャーに相談を受けることが出来ないケースも増えています。その負担を減少するため、更新費用の3分の2を補助する事業を四国で初めて導入しました。現在の人員数や、介護を受けられていないケースに加え、このまま現状が続いた場合のリスクなどを全て議会の場で話せたことが四国で初となる事業化の鍵となりました。
コロナ禍の中、介護・福祉・医療事業所へ補助金の交付
コロナ禍の中、介護福祉業界は、感染予防に努め、備品を自分たちで十分確保するようにという指導がありました。品薄の中必死にアルコールやマスクを探したことがあったと思います。そういった業界に対してしっかりとした補助をすべきだ。またその中で離職される方を少しでも防ぐため、事業所とは別に就業している方へも補助金支給を行うようにしました。業界が置かれている立場などの現状を的確に伝えられたことがこの事業導入の大きな鍵になりました。
このように現役介護職が政治家になることで、要望を出すだけでは変わらないことが数多く変わってきます。紹介した取組はそのうちの1部ですが、こうやって業界が少しでも働きやすい場所になるためにも、ぜひぜひ自分が政治家になって直接声を届けてみませんか。
まとめ
介護福祉職はどうしても政治の影響を受ける業界です。これまでは行政に命じられた中で必死に業務に取り組むのが美徳だったかもしれませんが、それは違うということに気づいてください。
黙っていては何も変わりません。声を上げる。その声を的確に届けるためのアプローチを学ぶ。
行政にとって使い勝手の良い奉仕者ではなく、誇りを持って働く業界人になるためにもぜひ政治に関心を持ってください。
この業界の未来を作るのはみなさんです。
▼今回の講師、山口大輔氏のホームページはこちら
https://daisuke.yamaguchi.jp/
グルホ研究会主催のイベントへの参加方法
グルホネットでは福祉事業者様向けのイベントを定期的に開催しています。福祉事業×専門家の講義が目白押し!次回開催のご案内や、障がい福祉事業向けの勉強会に関する案内を公式LINEで配信しております。
是非友達登録をお願いします! 皆様のご参加をお待ちしております!
![]()



